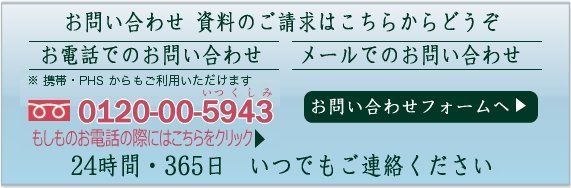HOME > お役立ち情報 > ご葬儀後の手続き
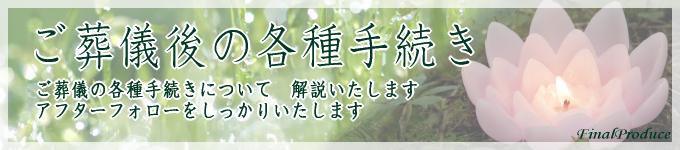
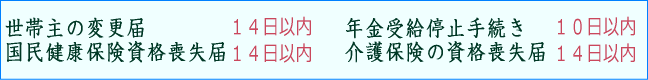
これらは期限がとても短いです。葬儀後一番初めにしましょう。
期限内に行わないと、よけいな手間がかかってしまうこともあります。
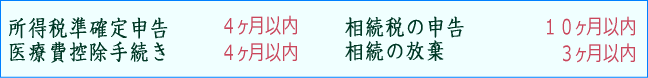
できるだけ早めに済ませることをお勧めします。
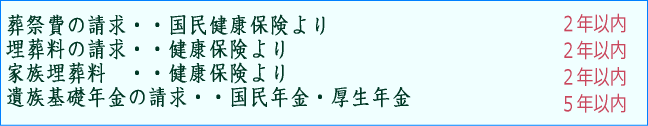
公的補助金も忘れずに給付申請をしましょう。一定額が給付されます。
加入されている保険により手続きが異なります
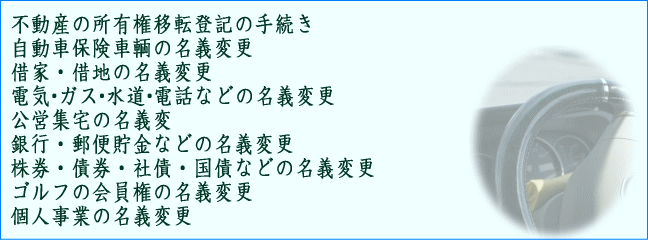
このような手続きはつい忘れがちになってしまいます。
該当するものがある場合はできるだけ早めに解約しましょう。
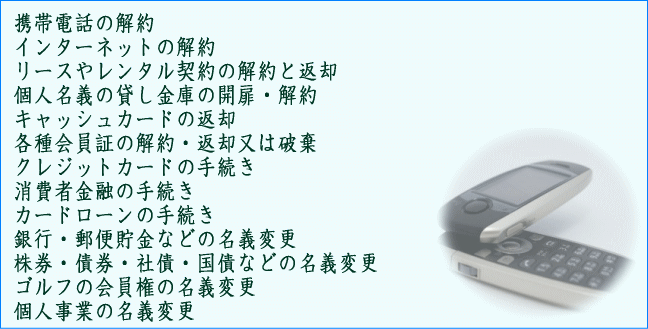
このようなものは、気がつかないでそのままにしていると会費を請求されたり、相続にも関わってきたりもしますので、確認して手続きするようにしてください。
手続き窓口や必要書類、その他の手続きにつきましても東京葬儀式社がご案内させていただきます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
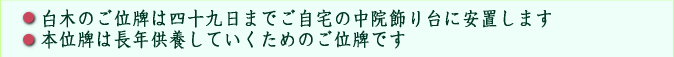
ご葬儀や野辺送りの際に使われる、仮の位牌が白木位牌です。
こちらはご葬儀の終了後、四十九日までの間、中陰飾り台に安置します。
本位牌は、御仏壇に安置され、末永く供養されていくためのご位牌です。
漆を塗り、金箔や金粉などで飾った位牌である塗り位牌が一般的です。
ご先祖様のご位牌がたくさんおありになる場合には回出位牌をご用意することもあります。
また、浄土真宗では位牌を用いません。
忌明けの際には白木の位牌は菩提寺にて供養を行っていただきます。
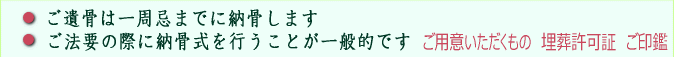
ご遺骨はご自宅にて安置したのち、納骨をします。
四十九日、百か日、一周忌などの法要の際に納骨式を行うのが一般的です。
納骨の際には、埋葬許可証とご印鑑が必要ですのでご準備をお忘れなく。
納骨式ではご親戚や、故人と親しくしていたご友人などにお集まりいただいて、行います。
菩提寺の僧侶に執り行っていただきます。
御仏壇は御本尊や花立、香炉などの仏具ともに四十九日の法要までに準備します。
長い間使っていくものですから、信頼できる御仏壇店でのご用意されることをお勧めします。
ご不明な点はどうぞお尋ねください。
仏式では、お亡くなりになって七日ごとに忌日法要を行います。
初七日はご葬儀の後にそのまま行うことが一般的になっています。
四十九日法要は、来世の行き先が決まるとされる、一番大切な日です。
この日に故人さまが極楽浄土に行けるようにと、法要を営むのです。
またキリスト教では、肉体の死は神とともにあることということになり忌明けの儀式はありません。